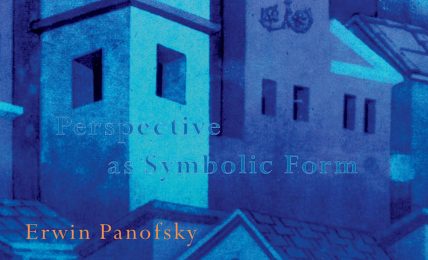ワークショップ「作品を見る/語る」に参加して
アナログ写真に関わる技術を学ぼうと思い、私(Toshiko Y)は東京オルタナ写真部のワークショップに参加しました。その流れで、プリントスタディやロラン・バルトの読書会にも参加してみました。そして、軽い気持ちで出席したプリントスタディで、私は言葉を失いました。いや、失ったというより、出なかったという方が正確です。
作品を批評するということ
プリントスタディでは、ある作品や展覧会を取り上げ、参加者同士で感想や批評を述べ合い、ディスカッションを行います。私はその場で、作品の印象を口にすることは出来ても、批評というものを行うことが出来ませんでした。他の参加者達の批評、そしてそれに対するディスカッションが頭上を飛び交う中、何をどうしたら良いのか、皆目見当がつかない状態に陥りました。
それでも、自分の好きな作品、自分にとってのいい作品というものは存在するのだから、それで十分でないか、と内心開き直っておりました。自分の感性で自由に鑑賞すれば、それでいい。それ以上の、ごちゃごちゃした批評がなぜ必要なんだろうか、と。
しかし、その時は気づいていませんでした。自分がいいと思う、ただそれだけで終わってしまうと、それ以上の広い世界が見えないままだということに。そして、いい、と感じるだけで、言葉にしないということは、自分の中で感動の理由を深く掘り下げていく行為がなく、その感動すら霧散してしまうことになるのです。
批評というと、どうしても欠点をあげつらう、というイメージですが、ここでいう批評というのは、そういう事ではありません。その批評により、作品の魅力が一層増し、未知の見方に誘われるという性質のものなのです。それは、新たな水平線を見せてくれる、あたかも水先案内のようなものです。
ワークショップ「作品を見る/語る」に参加して
このワークショップ「作品を見る/語る」を体験した後では、私はもはや自分の見方のみを信ずる自由気ままな鑑賞が成立するとは、思えなくなりました。
自分の視線というものは、そもそも無垢なものなのだろうか。自分の置かれている立場、環境、文化、時代に影響されているものではないのだろうか。そもそも、自由に鑑賞するとは?何からの自由なのか?通説?常識?偏見?あるいは、無知?今回の私は、まさにこの自分の無知が、自分を縛っていました。無知は即、偏見や誤解につながります。正しい基礎知識の上に立たない限り、真の自由を手にすることは出来ないのです。
一方で、批評文として正しくありたいという欲求は、どうしても歴史的背景や作者に寄り添った見方に傾きます。当然のことながら、鑑賞はそれのみで成立するものではありません。バルトの言うところの「作者の死」、この概念をこの講座を通じて初めて実感しました。作者から離れて、自由に作品を鑑賞するためにも、やはり基礎的な素養は必要なのです。その上に立って、作者に適切な死を与え、自分の批評を成立させることが出来るのです。
そして、批評文を書ききってしまうと、今度はその意味の固定化に対する不安に襲われました。言葉に表すことにより、自分の見方が言葉によって固定され、逆にそれに縛られてしまうのではないか。だからこそ、他の人とのディスカッションが、非常に有益なのです。多面的な見解により、一人では成し得ない、より豊かな鑑賞体験をすることができます。一人一人の批評が、あたかも一つ一つの断章のように、作品に迫っていく。そのスリリングな体験は本当に興奮するものでした。
感動の全てを言語化できるという事ではありません。言語が及ばす、ただ純粋な感動としてのみ残るものもあるでしょう。しかし、だからと言って、言語が無力だということではありません。自分がいいと感じればそれでいい、という鑑賞態度では到達しえない感動の高みへ、言語を用いた批評によって、我々は到達することができるのです。
作品を言葉にすることで何が起こるのか
まさに、今後の人生が変わったと言っても過言でないほどの講座でした。
バルトの読書会の内容や、アドバンストクラスの美術史の話、そしてプリントスタディ、全ての流れがつながって、実感として一つになった時、鳥肌立つような感動を覚えました。高揚感が半端なく、その夜はなかなか寝付かれない程でした。アナログ写真の技法の講座が、私にとって画期的であるならば、こちらの講座はアートに関わっていく精神面で、革命的でありました。
以下は、私がこのワークショップで執筆した批評です。
国立西洋美術館の常設展で展示されている「ホロフェルネスの首を持つユディト」ルカス・クラーナハ(父)を取り上げました。
作品批評:「ホロフェルネスの首を持つユディト」 ルカス・クラーナハ(父)
©Toshiko Y
ルカス・クラーナハ(父)は、16世紀ドイツの画家で、ザクセン選帝侯フリードリヒ3世が宮廷を置いたヴィッテンベルグに工房を持ち、御用絵師として多くの肖像画や宗教画を描いた。ドイツ・ルネサンスを代表する画家のひとりと言われている。
ユディトというのは、旧約聖書の『ユディト記』に登場するユダヤ人女性のことである。ユディトは、ユダヤのベトリアに住む、神への敬虔な信仰を持った美しい未亡人であった。ある日、アッシリアの軍隊がベトリアに侵攻し、街を包囲し、水源を絶ってしまう。ベトリアの指導者と住民たちは降伏しようするが、ユディトが神への信頼を訴えて反対し、一計を案じた。美しく着飾ったユディトが、アッシリア軍の将軍であるホロフェルネスに面会を求め、エルサレム進軍の道案内を申し出る。4日目にホロフェルネスは、ユディトを酒宴に呼び出すが、やがてホロフェルネスが泥酔すると、ユディトはその首を切り落とし、ベトリアの町をアッシリア軍から見事に救ったのだ。
このユディトのテーマは、多くの作家により繰り返し描かれている。クラーナハによるユディトも、現存するだけで10数点が知られている。
西洋美術館所蔵の「ユディト」に描かれているもの
西洋美術館所蔵のユディトであるが、落ち着いた表情で、全身から強い意志と冷静さが感じられる。しかし同時に身体は細く、危うく、脆い印象も受ける。服装は、さながら騎士の様ないでたちで禁欲的で、ややもすると中性的だ。
その一方で、ふっくらとして色づいた頬、優美な身体の曲線は、女性らしさを表している。身体は暗がりで光る直線的で重厚な剣と際立った対照をなしており、衣服の下の裸身への想像をかき立てる。禁欲的な衣服に包まれていてもなお匂い立つような、女性の魅惑的な肉体が描き出されている。露わでない分、余計に官能的魅力が引き立っていると言えるかもしれない。
背景を見ると、右上部には窓が抜かれ遠景に山々と麓の町が垣間見れる。窓に風景画が取り入れられことや、その青味がかった色彩は、当時のイタリアルネッサンスの影響、そして空気遠近法の技法が見て取れる。この窓の風景があることにより、画面全体により奥行き感が生じ、暗闇がより暗く感じられるようになっている。窓から見える町の景色は、町の命運を背負ってやってきたという、ユディトの使命感の心象風景とも受け取れる。
成熟した女性の身体でホロフェルネスを魅惑しつつ、冷静に町のためにその首を討ち取ったユディト、そして使命を達成したあとの緊張感を孕んだ静けさ、この絵ではそうしたユディトの物語が十分に描かれている。
クラーナハは、宗教画としてのフォーマットを取りながら、彼女を歴史上の人物としてではなく、自分の女性像として描こうとしているのではないか。男を惹きつけ惑わすその官能的肉体とその裏腹な冷徹さ、ユディトの持つこの取り合わせが、クラーナハにとっては、大変に魅力的なモチーフであり、自分の持つ女性像にも重なるものがあったのではないだろうか。
クラーナハが描いた「ユディト」と「サロメ」
クラーナハの描いたユディトで、より有名な作品が、ウィーン美術史美術館蔵のユディトであろう。こちらのユディトは、圧倒的な官能的魅力を醸し出している。しかし、肉体からは溢れんばかりの魅力を発しながらも、その表情は固く、わずかにすがめられた右目や力の入った唇から、使命を遂行しえた冷徹さを垣間見ることができる。

また、このウィーンのユディトによく似た絵が、ブタペスト国立美術館にある、「洗礼者ヨハネの首を持つサロメ」である。この絵を見ると構図やモチーフにおいて、西洋美術館とウィーンの「ユディト」との類似性が認められる。しかし、その表情には大きく隔たりがある。ウィーンのユディトが伏し目がちで冷静で硬質な表情であるのに対し、ブタペストのサロメの表情からは、狡猾で抜け目がない印象を受ける。両者共に、自分の官能的魅力で男を死に追いやるという女であっても、同じように描くのではなく、その人格の相違を、クラーナハは細かく表情を描き分けている。各々、よりふさわしい表情、感情表現として、描いているのだろう。

宗教画の中の人間性
そして、振り返って、西洋美術館のユディトを見てみる。瞳は澄んで理知的であり、こちらを真っすぐに見据えている。そして、控えめな装飾と凛とした立ち姿。クラーナハは、この絵でユディトを宗教画として描きながら、同時に、冷静で理知的な様相と魅惑的な肉体、危うさと強さという、相反する事項を持つ女性像を描いているのである。外面にも内面にも落差が感じられるこのユディトの絵は、控えめな色使いと装飾で、一層ユディト自身が引き立ち、この小ぶりな絵の前に立つと、その落差が均衡している緊張感に引き込まれる。従来の形式的な宗教画を超えて、人物の人間性を描き出そうとしているルネサンスの空気が感じられる作品である。