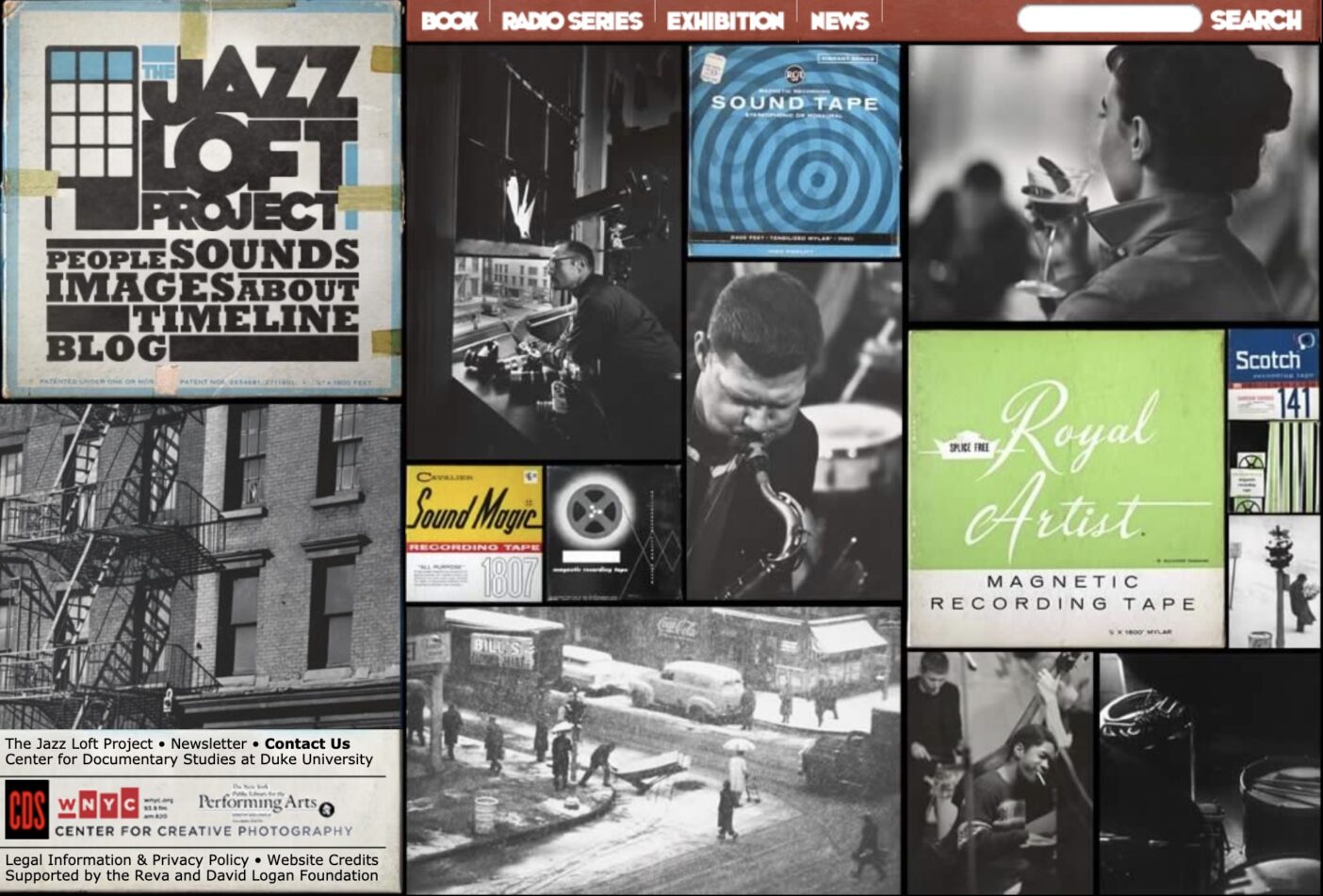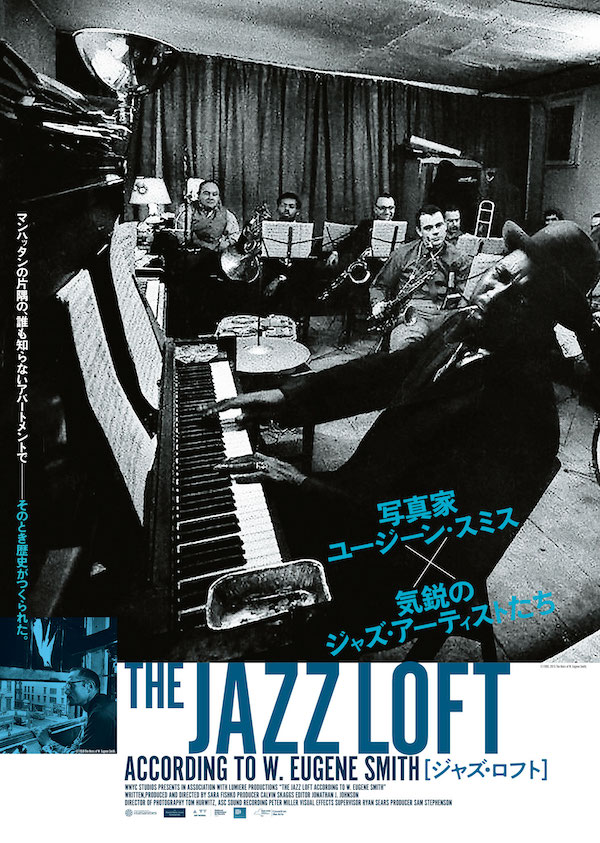東京オルタナ写真部ではユージン・スミス研究会を開催予定だったが、ユージン・スミスとフォトジャーナリズムについて客観的評価をするには時期尚早だと判断し、開催を延期した。関心ある方のために参考になる資料を挙げておく。
ユージン・スミス研究会
この研究会はユージン・スミスを通じて、20世紀のフォトジャーナリズムとその時代を探ることを当初の目的としていた。そのための3つの主要なトピックを想定していた。
雑誌『LIFE』
20世紀のフォトジャーナリズムを作った写真グラフ誌。ユージン・スミスのフォトエッセイがそのスタイルにどう寄与したのかを検討する。また、マグナム・フォトなどのフォトエージェンシーと『LIFE』との関係から、当時の写真家を取り巻く環境を考察する。
ジャズ・ロフト
表舞台から隠遁したユージンがこもった倉庫ビル。キャリアと家族を捨てた彼はなぜアンダーグラウンド・ジャズシーンに埋没したのか。1950年代後半のNYジャズシーン、そしてロフトに代表されるサブカルチャーの分析。
『MINAMATA』
近代産業が人々の暮らしを破壊した公害病。なぜユージンは、遠い日本で起きた事件に身を投じたのか。水俣病が現代に投げかける意味と共に、ユージンの最大の仕事を読み解く。
ユージン・スミス関連映画
映画『LIFE』
日本語タイトル:「ディーン、君がいた瞬間」
駆け出しの写真家デニス・ストックと新人俳優ジェームズ・ディーンの短期間の交流を描いた映画『LIFE』。この時期の写真家が生きた世界が垣間見られ、興味深い。マグナム・フォト(フォトエージェンシー)や雑誌『LIFE』との関係、カメラ機材、撮影方法、取材方法、問題の絶えないプライベート…。そして手の届かない有名写真家ユージン・スミスの個展の案内を苦々しく手に取るシーン!若い無名写真家の嫉妬や焦燥感、そして当時のユージン・スミスの存在感が描かれており、映画『ジャズ・ロフト』の前日譚的な作品として見ることができる。


映画『ジャズ・ロフト』
『ライフ』編集部と決裂したユージン・スミスは、家族も捨てて、音楽家や画家たちが不法に住んでいるニューヨークの倉庫ビルに移る。そこにはピアノやドラムがセットされ、セロニアス・モンクらが出入りして連日連夜ジャムセッションを繰り広げた。アンディ・ウォーホルの「ザ・ファクトリー」を先取りするような拠点となったニューヨーク 6番街 821番地。ユージン・スミスは建物中に配線し廊下にまでマイクをセットし、オープンリールテープ4,000時間分を録音し、400,000枚以上の写真を撮影した。
このテープと写真はライターのサム・スティーブンソンによって発見され"The Jazz Loft Project"という本にまとめられて出版される。
映画『ジャズ・ロフト』はこの本を元にしたドキュメンタリー。複雑で問題の多いユージン・スミスの肉声(文字通りの意味)が聞ける。
映画『ミナマタ MINAMATA』
水俣病に取材したユージン・スミスの写真集『MINAMATA』を原作とした映画。NYロフト時代から始まり水俣病取材のユージン・スミスを描く。しかしこの映画の内容は事実ではない。水俣病とユージン・スミスの両方に対して誤解を招く内容があり、かなり問題のある作品。ユージン・スミス関連の参照資料として扱うには注意が必要。

以下はこの映画のストーリーを構成する中心的なエピソードだが、いずれも実話ではない。
- ユージン・スミスを訪ねたアイリーンが水俣病の取材を依頼する
- 加害企業チッソが公害の原因事実を知りながら隠蔽していたことをユージンが暴露する
- チッソがユージンの買収を試みるが拒否される
- チッソ協力者によってユージンの暗室が放火され、ネガが失われる
- ユージンの写真記事がチッソ上層部を動かして住民補償が実現した
チッソが、水俣病の原因が自社の工場排水であることを知っていながら隠蔽していたことは事実だが、それをつきとめ糾弾したのは、長い年月をかけて現地で原因究明に取り組んだ原田正純をはじめとする医師たちである。ユージン・スミスはこの件について関係していない。しかし映画『ミナマタ』では、チッソに忍び込んだユージン・スミスとアイリーンたちが隠されていた資料を発見し、事実を公にしたことになっている。これは明らかな事実の歪曲であり、他人の努力と成果を盗み、すげ替える行為にほかならない。
「その場にいたはず」のアイリーン・スミス本人は、この映画のストーリーが事実でないことを認めながら、映画で水俣病が多くの人に知られるのは良いことだとコメントしている。彼女はこの映画に関するインタビューでしばしば、客観性を手放すことの積極的な意義を語っている。これは「事実を偏見にする(let truth be the prejudice)」というユージン・スミスの奇妙なスローガンを受け継いだものだが、事実を放棄したフォトジャーナリズムは陰謀論や歴史修正主義と区別できないものになるはずだ。
この映画が示唆しようとする「真実」については、映画制作サイドの事実に対するこういった姿勢を踏まえた評価が必要になる。
ひとまず、この映画のプロットは事実を描くのではなく「真実のために巨悪と闘った偉人ユージン・スミス」という実在しないキャラクターを創作することを目的にしていると指摘できる。そのため、この映画を資料として扱う場合は「ユージン・スミス」という虚像が成立し再生産する過程を示す歴史資料としてのみ扱うことができる。
映画ライター冨永由紀による記事
大義があれば虚実を気にするのは無意味なのか。感動と複雑な感情が入り混じる『MINAMATA―ミナマタ―』
Newsweek記者 大橋希による記事
雑誌『LIFE』
LIFE 1936年に創刊されたアメリカの写真グラフ誌。レイアウトされた組写真でニュースをストーリーとして伝える「フォトエッセイ」の手法を生み出した。ユージン・スミスは1943年から『LIFE』誌に写真を提供していたが編集部と衝突し1954年に辞職する。『LIFE』誌は1960年代からテレビの普及に押されて縮小し、2007年に休刊。
Google Booksによるアーカイブ
1936年の創刊号から1972年発行分までGoogle Booksでアーカイブされている。
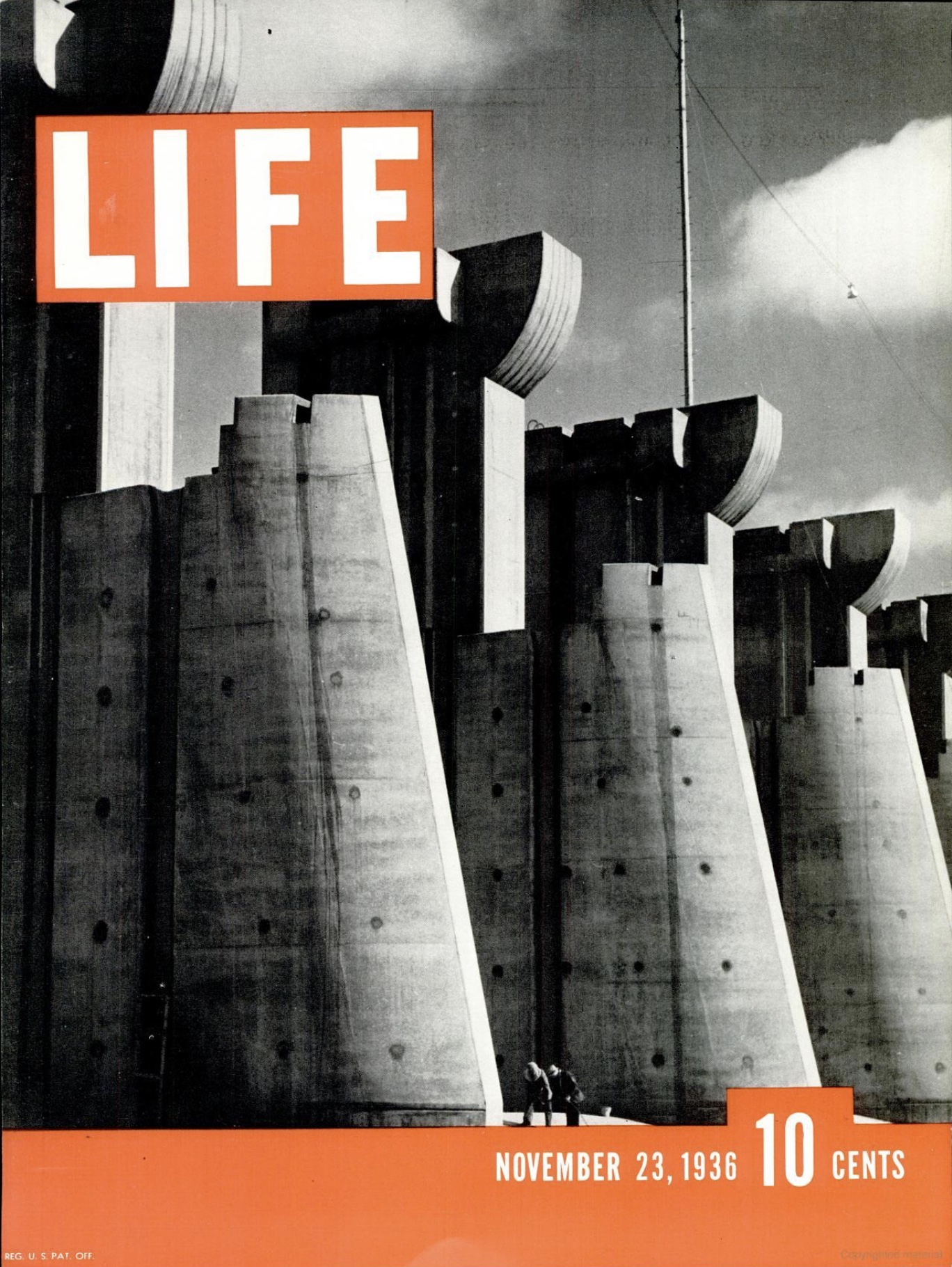
MAGNUM Photos マグナム・フォト
MAGNUM PHOTOS 1947年設立の写真家による協同組合。写真家たちが自ら計画した取材活動などを支援するフォトエージェンシー。ユージン・スミスは『LIFE』と決裂した後の1955年にマグナム・フォトに参加する。ピッツバーグ市を写真で記録するプロジェクトを任されるが、ここでもユージンは極めて独善的に仕事をしたため、マグナム・フォトとの関係は悪化する。
W. Eugene Smith: Master of the Photo Essay
W. Eugene Smith’s Warning to the World

水俣病 参考リンク
水俣病は1930年代に始まっており1968年に原因が正式認定されるまで、すでに長期にわたる被害と闘いがあった。水俣の住民の苦しみと現代文明の行き詰まりを黙示録的に描いた文学作品、石牟礼道子の『苦海浄土』が出版されたのは1968年。医師、原田正純が原因特定までの長い闘いの記録を出版したのは1972年。
ユージン・スミスが水俣で取材に1971年から3年間をかけたとはいえ、それはすでに加害と被害の関係が確定しており、市民が企業を糾弾するという構図ができあがった後の3年間だった。ユージン・スミスが水俣の取材をLIFE誌に掲載したことでこの公害事件はさらに注目を集めることになった。しかしある見方をすると、ユージン・スミスは有名雑誌にコネクションがある写真家で、ストーリーになりそうな対象を見つけて取材したに過ぎない。彼は写真を撮りそれを組み合わせて、ショッキングだがわかりやすく消費できるストーリーを作ったが、それ以上のことをしたわけではない。
原田正純『水俣病』
水俣病の原因究明に取り組んだ医師の手記。地を這うような調査と、現代医学への厳しい批判と反省が胸を打つ。
石牟礼道子『苦海浄土』
歴史に類を見ない規模の公害を人類が直面する課題として提示した世界的文学作品。
NHK 100分de名著
ユージン・スミス写真集『MINAMATA』
フォトジャーナリストの評価とは:広河隆一の事例
広河隆一は日本の代表的な「人権派」フォトジャーナリストだ。その彼が深刻な性犯罪加害者でありパワハラ加害者であったことが告発されたことは記憶されている方もいるだろう。
セクシャルハラスメントの告発に対して広河は当初極めてエゴイスティックな言い逃れを行った。
写真の仕事(作品)と作家個人の評価は分けるべきだという見方はあるだろう。しかし広河隆一が、人権問題について見識の深いジャーナリストとして広範な媒体で長年仕事をしてきたことは事実だ。「人権」は広河の大きなブランドだった。しかし実際には彼は深刻な人権侵害の加害者だった。
広河の事件は、日本の写真界に深く後戻りできない衝撃を与えたと思われたが、実際はそうではなかった。広河が設立した団体「日本フォトジャーナリズム協会」は道義的精算を検討する様子もなく存続している。
ユージン・スミスについて話を戻すと、彼は明らかに人格破綻の傾向があり家族生活を捨てたことでも知られている。非常にエゴイスティックな性格であったことは事実だ。当然ながら、この研究会ではユージンの人物像と彼の仕事とは分けて分析するつもりだった。しかし現在もユージン・スミス当人を高邁な人格者であるかのように評価する風潮が定着しており、多数派の見解として圧力も帯びている(『ミナマタ』の映画評を書いたライターの冨永由紀は、大義を盾にした相手への批判は呑み込まなくてはならないのか、と書いている)。
ユージン・スミスや、他のフォトジャーナリストを客観的に評価するには、まずその前にフォトジャーナリズムとは何なのかを冷静に評価し直す必要がある。マスメディアを通じた影響力に過ぎないものを見誤り、写真家に対して信じられないような過大評価をしていないか、そこから改めて検証する必要があるだろう。