ソフィ カル 廃墟化する現代美術
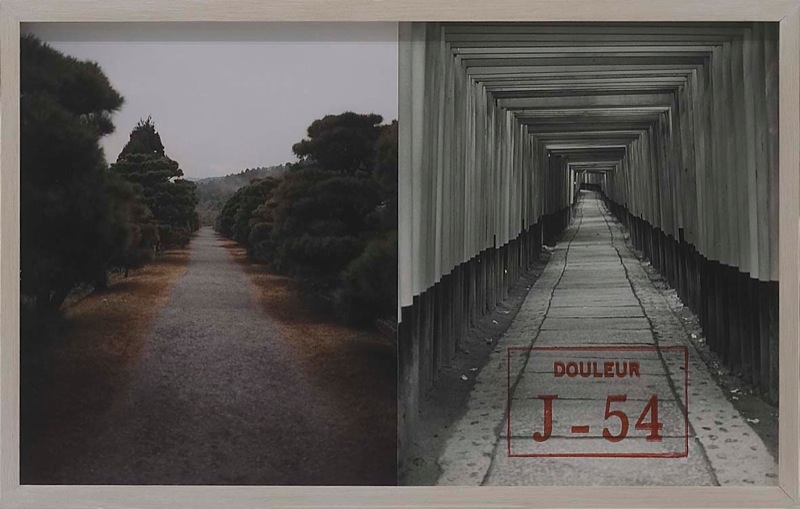
プリントスタディでのディスカッションでは、ざっくりまとめると
「不快だった」
「みんな同じようにして心痛を乗り越えてるよね」
というふたつの感想が得られたと思います。
引き続き、それぞれについてもう少し考えてみたいと思います。
「不快だ」という印象のもとになったのは何か。
個人的な好き嫌いの感覚は置いたとしても、この作品は倫理的でないという意見がありました。なぜそのように感じるのか?いやそもそも、芸術表現に倫理は問えるものなのでしょうか?
私たちは「表現の自由は保護されなければならない」という通念を社会的に共有しています。しかしそれでも表現行為においてNGとされていることはあります。剽窃や盗作などがまずそうですね。もっともこれらも突き詰めると境界はあいまいです。デザイン、オマージュ作品、批評的表現などにおいては盗作かどうかは見極めが難しい問題です。しかしもし、明白な盗作とみなされた場合は、倫理にもとる行為だとされます。だって人のものを盗んでいるんですから。
ソフィ・カルの作品が倫理的でないという印象を与えるのも、もしかすると彼女は何かを盗んでいるからではないか…というのはあくまで私の直感です。とはいえそれを仮説にして、もう少し考えてみます。
この作品では、ソフィ・カルが失恋で心に痛手を負い、そこから回復するまでの経過が示されています。では、彼女はどのような経緯をたどったのか。
失恋したソフィ・カルは、話を聞いてくれる人をつかまえては自分の失恋話をします。そして相手にも自分におこった不幸な出来事を話してもらいます。この他人の不幸話とソフィ・カルの失恋話が、交互に展示されています。他人が語る不幸は、陰惨なひどい話ばかりです。それを聞くにしたがい、人に話すソフィ・カルの失恋話はだんだんと内容が変わっていきます。ソフィ・カルの失恋話はどのように変わっていくのか、彼女の話は最後はこうなります。
こんな失恋話は、どこにでもよくある話だ
陰惨な他人の不幸に比べると、自分の失恋なんてどこにでもあるよくある話に過ぎない。こう結論することが彼女のゴールだったわけです。これは非常に興味深かったです。なぜなら、これはロラン・バルトとは完全に逆のことをやっているから!
まさに、他人の不幸は蜜の味!
プリントスタディのディスカッションでは、自分の痛みは本当に一般化や相対化なんてできるのだろうか、という話題がでましたが、確かにそのとおりです。どんなにありふれた出来事であったとしても、私の喜びや痛みは、私にとっては私だけの意味があります。
個人的な話ですが、私は20代の頃、生きていることの辛さを打ち明けた友人から「みんな苦しくても、それでもやっていってる。お前だけが苦しいわけじゃない。」とアドバイス(?)を受け、びっくりしたことがあります。それぞれの人の苦しみは、それがありふれてようがなかろうが、それぞれの人に固有のものではないのか?そんな一般化がどんな解決をもたらすのか?もし、自分の問題を一般化することが解決なのだとしたら、自分の苦しさについて自分で考えることさえ許されないではないか?
自分にとっての意味に向き合い考えるか、問題は一般化してやり過ごすという処世術を優先するか。そのどちらを選ぶかが、私とこの友人の違いでした。またこれがロラン・バルトとソフィ・カルの違いだと言えます。そして、ソフィ・カルは、自分の問題を一般化してやり過ごす方を選んだわけです。

彼女が自分の失恋の痛みを一般化したやり方は、他人の不幸な話を聞き出し、それと比較し相対化するという方法でした。もし彼女が何かを盗んでいるのだとしたら、それは、他人の不幸の意味ではないかと思います。彼女が自分の失恋を一般化するのは自由です。それは失恋ものの小説を読んだりしても可能だったでしょう。しかし彼女は、現実に生きている他人の現実の経験を利用します。それらの不幸の経験は、現実に生きられたものであり、いまもその人だけの意味を持つ出来事です。しかしソフィ・カルはそれらの不幸の経験を自分の失恋と同じように一般化して並列化します。この行為によって彼女は、ある体験がその人にもたらす固有の意味を盗んでいる、と言えるだろうと思います。
この剽窃行為が、彼女の作品に倫理的な問題を生じさせているのではないでしょうか。本当は相対化できないはずの個人の内的な痛みを相対化してみせるという行為自体も、乱暴であり不誠実だと言えるかもしれません。そして自分の体験のみならず、他人の体験に対しても同様に一般化してみせた。その動機は2つです。ひとつは自分が負った痛手を相対化して「解決」するため。もうひとつは、「作品」を作るためです。ここに彼女のエゴイズムを感じるのは自然なことだと思います。

ところで彼女が他人の経験を一般化した方法は、それを「現代美術作品」というフォーマットに変換することでもありました。私たちのディスカッションでは「この展示は現代美術というコンテンツビジネスではないか」という見解も出ましたが、それは、この彼女の方法によるものだと考えられます。これも非常に興味深い問題を示しています。
他人の不幸を、固有の意味を剥ぎ取って展示する。なぜなら、ソフィ・カルにとっては、不幸や痛みは一般化できれば解決できるものとして捉えられているからです。
ものごとの一般化を可能にするものは、すでに広く社会に認められて、ある種の権威や威信として機能するような概念です。例えばそれは「みんながいいねって言ってるもの」です。みんながいいねと言うと、それ自体の意味はもう問われることなく、それが「正しいこと」になっていきます。具体例は割愛しますが、思いめぐらせばいろいろありますよね。「勝てば官軍」「寄らば大樹の陰」みたいな感じです。
そしてソフィ・カルがこの展示に際し、自分と他者の不幸を一般化するために利用した「権威・威信」は現代美術です。これは非常に面白い!なぜなら、その現代美術とは、かつての古い美術が持っていたこのような権威や威信を解体することを至上命題にして始まったものだからです。

19世紀的な近代美術は、たとえば「作品とは私の内面が表現されたものである」というような考えを強く持っていました。そこでは「私」とは何か、「表現」とは何かは問題にされなかったのです。
美術作品であれば、それは価値のある表現である。(古い美術の価値観)
その凝り固まった権威に挑戦したのが、かつての現代美術でした。
しかし、ここでソフィ・カルが一般化のために利用している現代美術という権威・威信は、まさに古い美術が社会に対してもっていた力と同じものです。ソフィ・カルを見る限り、現代美術は、昔の美術を解体したのではなく、ただ、代わりのものを置いただけに見えます。パッケージが違うだけで中身は同じといったところでしょうか。この視点に立つと、ソフィ・カルの展示は、現代美術の失敗を露わにしているというように見えます。
これは私の感想ですが、ソフィ・カルの展示はたいへん古臭く見えました。発想が本質的に昔の美術と変わっていない、というのも理由のひとつです。しかしそれ以上に、「私」や「意味」や「表現」といった概念を捉えるセンスが、あまりに時代遅れで弛緩している、というのが大きな理由です。それはこの作品がいまから20年以上前に制作されたからではなく、制作当時においてすでに時代遅れなものだったのです。
ロラン・バルトは「私を私にしているものは何か」を考えようとしました。彼はそれを考えるために、自分の問題を一般化することに徹底的に抵抗するという方法を探ります。それが現代的な思想の課題だと確信していたからです。それはまた、「私」や「作者」が作品の主人になることなく表現の意味を問うことはできるか、という問いでもありました。これはまさに、かつて現代美術が挑んだ問題そのものです。
ロラン・バルトがこのような挑戦のもとに書いた本『恋愛のディスクール』や『明るい部屋』が出版されたのは1980年です。ソフィ・カルがこの失恋を経験したのは1984年。この作品が制作されたのはさらにあとの1990年代です。ロラン・バルトの先鋭的でスリリングな挑戦とくらべると、その後に制作されたにもかかわらず、ソフィ・カルの作品には全く時代遅れな閉塞感を感じてしまいます。
「現代美術というコンテンツビジネス」という指摘には最初は過激だなと思いましたが、考えていくうちにそれは妥当な評価かもしれないと思えてきました。それは最終的に、この作品からは「現代美術という文脈に沿うような活動をプレゼンテーションする」ということ以上の目的を受け取ることが難しいように感じるからです。
とっくに消費期限の切れた「現代美術(というコンテンツ)」が廃墟のように朽ちていく様を見ている。正直なところ、そのような印象も覚える展示だったと思います。
また、ソフィ・カルは、他人が体験した陰惨な出来事を陳列することで、見る人に感情的な動揺を与えることを意図して展示を構成しています。それが表現として価値や意味があるかどうかは、目的によって評価されるべきです。
ソフィ・カルのこの作品は、その点でも積極的に評価できるかどうか、少し疑問に感じました。何か大事な問題から目を逸らさせる、あるいはそもそも重要な問題が存在しないことを隠すことが目的で、このような感情を動揺させる構成が選ばれているのだとしたら、それは表現を騙る行為です。それは芸術という文化制度そのものに対する「剽窃」だと言えるかもしれません。
以上のような批評には「倫理観を揺さぶり、議論を起こすことにこの作品の意図がある」という反論もあるかと思います。しかし、倫理に挑戦するのが芸術だと言うだけであれば、それはもはや犯罪と区別のつかないものになってしまいます。
表現の倫理については以前、短い文章を個人ブログに書いたことがあります。もし関心がありましたら下記リンク先の記事もご参照ください。
表現と犯罪 (Kenshi Daito photograph)

ここでも取り上げた「私」と「表現」という問題。これに関する読書会を開催します。次回の読書会で取り上げる本は『ロラン・バルトによるロラン・バルト』ご関心ある方はぜひご参加お待ちしています!
またプリントスタディは定期的に開催しています。そちらもどなたでもご参加いただけます。またプリントスタディで取り上げてほしい展覧会がありましたら、ぜひお知らせください。
